- TOP
- COFFEE BREAK
- エッセイ*赤川次郎【コーヒー色の回想。】
- エッセイ*赤川次郎【コーヒー色…
COFFEE BREAK
文化-Culture-
エッセイ*赤川次郎【コーヒー色の回想。】

「いつも喫茶店ですね」
と、よく言われる。
私自身のことでなく、私の小説の登場人物のことだ。もちろん、それはアルコールの全く飲めない私が、バーという所はほとんど出入りしたことがないせいでもある。
おかげで、私の小説の登場人物はビールもカクテルも口にできず、時には甘味喫茶でお汁粉をすするはめになる。ロマンチックな会話は弾みそうにない。
私が作家になった、今から四十年ほど前には、至る所に喫茶店があって、編集者との打合せはたいてい新宿辺りの喫茶店だった。
今でも忘れられないのは、『セーラー服と機関銃』が薬師丸ひろ子君で映画化されることになって、監督と初めて会ったときのことだ。まだ昼間の喫茶店に、相米慎二監督は少し酔っ払って、赤い顔をして入って来た。
役者を厳しくしごくことで知られた相米監督だが、一面大変な照れ屋でもあって、原作者との対面に、素面では来られなかったのだろう。ほとんど打合せらしいことはしなかったと思うが、開口一番、
「同い年なんだよなあ」
と言ったのは憶えている。
残念なことに、相米さんは早世してしまったが、今思うと、私が酒飲みなら、きっと一杯やりながら話したかったのだろう。
――夜中から明け方まで仕事をして、それから寝る、という私の生活パターンは、作家になって四十年、変らない。夜中の仕事にはやはりコーヒーが欠かせない。小説の中で、主人公がおいしいコーヒーを飲んでホッとしていると、私も飲みたくなる。そういう場面では、たいてい私も机から離れてコーヒーをいれに行っているのである。
仕事中と昼間の打合せで、合せて結構な量のコーヒーを飲むけれど、「味」に関しては、さっぱり分らない。「この店のこの豆でなくては」といった通では、全くない。
それでも、多少味にこだわるようになったのは、ウィーンにしばしば旅をしてからのことだ。周知のように、ウィーンでは「カフェ」が一つの文化として根づいていて、百年を超える歴史のあるカフェが何軒もある。
かつては作家や画家などが一日中カフェに座って、自宅の客間のように利用していたという。初めてウィーンに行ったとき、せっかくだから、「ウィンナコーヒー」を頼もうとしたら、ガイドさんに、
「ウィーンにウィンナコーヒーはありません」
と言われた。
確かに、どのコーヒーを頼んでもウィンナコーヒーに違いない。最も一般的に頼むのが「メランジェ」で、ウィンナコーヒーのイメージに近い。メランジェを頼むと、なぜか水のグラスが付いてきて、そのグラスの上に、渡すようにスプーンが置いてある。長年の伝統なのだろうが、理由はよく分らない。
ともかく、伝統あるカフェで飲むメランジェは深みがあっておいしい。それぐらいは私にも分るのである。
ウィーンでよく泊ったホテル・インペリアルのカフェは、かつてワーグナーも訪れていたそうだが、私も、ここでコーヒーを飲んでいて、ウィーン・フィルのコンサートマスターだったキュッヘルさんを見かけたことがある。指揮者のズービン・メータが、ハンドバッグ一つだけの夫人の後から、両手にいくつもトランクをさげてやって来るのを見てびっくりしたことも......。
メータは今年、ウィーン・フィルと来日するが、八十才と聞いて愕然とする。精悍なイメージだったが、すっかり太ってしまった。
人のことは言えない。
新人賞をもらってから二年間、サラリーマンを続けながら書いていたときだ。シナリオライターに会うことになって、TVのプロデューサーと喫茶店に入って待っていた。プロデューサーも、そのライターさんとは面識がなかったのだが、フラリと入って来た、少し太めのラフな服装の男性を見て、すぐにその人だと分った。
「あの手の仕事の人は、たいていああいう感じだよ」
と言われて、背広にネクタイだった私は、そんなものかと思った。
今、正に鏡の中を見れば、その通りの人間が立っている。不規則な生活、運動不足。
色々原因はあろうが、少なくとも、コーヒーを飲んでもやせないということは確かである。
さて、これを書き終えたら、コーヒーにしよう。せめて、砂糖は入れないことにして......。
1948年生まれ。作家。76年『幽霊列車』で第15回オール讀物推理小説新人賞を受賞しデビュー。「三毛猫ホームズ」、「鼠」シリーズ他、『セーラー服と機関銃』などベストセラー作多数。2006年、第9回日本ミステリー文学大賞受賞。


 健康
健康 美容
美容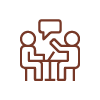 インタビュー
インタビュー 文化
文化 世界のコーヒー
世界のコーヒー 基礎知識
基礎知識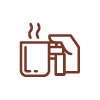 楽しみ方
楽しみ方